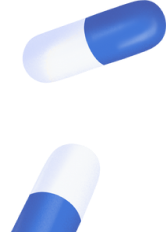医療事件チームでは、定期的に判例の勉強会をしています。
今回は、東京地判令和4年12月22日判決をご紹介します。
1 概要
造影CTや造影MRI検査をしなかった過失や腹部CT検査で肝細胞癌を見落とした過失があるとして損害賠償を求めたが、棄却された事例
- 結果 請求棄却
- 原告 患者(死亡時69歳の男性)の相続人
- 被告 大学病院
- 分類 消化器・肝臓内科
2 医学的知見
・肝細胞癌のステージ
肝細胞がんの病期(ステージ)は、がんの大きさ、個数、がんが肝臓内にとどまっているか、他の臓器まで広がっているか(転移)によって決まる。
・肝臓の障害の程度を示す指標
肝障害度(肝予備能。肝臓の機能がどのくらい保たれているか)は、肝機能の状態によって、A、B、Cの3段階に分けられる。また、肝硬変の程度を把握するための指標として、Child-Pugh分類が用いられる。
Child-Pugh分類は、脳症、腹水、血清ビリルビン値、血清アルブミン値、プロトロンビン活性値の各項目につき、それぞれ何点に当てはまるかを確認し、合計5から6点が分類A、合計7ないし9点が分類B、合計10ないし15点が分類Cとされる。
・肝臓病の治療の選択
肝臓癌の治療としては、がんとその周囲の肝臓の組織を手術によって取り除く外科的手術である肝切除、穿刺局所療法であるラジオ波焼灼療法(RFA)、塞栓療法である肝動脈化学塞栓療法(TACE)及び肝動脈塞栓療法(TAE)等があり、肝臓の状態やがんの進行具合によって、分子標的薬による薬物療法や、肝移植、放射線療法を選択することがある。
肝細胞癌の治療方法の選択に当たっては、肝細胞癌患者の多くが、癌に加え慢性肝疾患を抱えていることから、がんの病期(ステージ)だけでなく、肝臓の障害の程度(Child-Pugh分類による評価)も考慮する必要があるとされる。
日本肝臓学会作成の平成29年公表の肝がん診療ガイドライン2017年版(以下「本件ガイドライン」という。)の治療アルゴリズム(以下「本件治療アルゴリズム」という。)によれば、肝予防能がChild-Pugh分類Bで肝外転移、脈管侵襲がなく、腫瘍数が1個、腫瘍径が3cm以内であれば、治療法として、切除又はラジオ波焼灼療法(RFA)が推奨される。他方、肝予備能がChild-Pugh分類Cの症例で,患者年齢が65歳以下であれば、肝移植が推奨されるが、Child-Pugh分類Cで、肝移植不能であれば、緩和ケアが推奨される。
また、本件ガイドラインでは、Child-Pugh分類Cの症例では、治療による肝不全や合併症のリスクを考慮すると、移植以外の積極的な治療を推奨するまでには至らないとされている(強い推奨度)。
・PIVKA-‹2›値
PIVKA-‹2›は、肝臓で合成される血液凝固因子であるプロトロンビンの合成過程において、必要とされるビタミンKが不足することにより生じる、凝固活性を持たない異常蛋白である。ビタミンKの欠乏時に高値となるが、肝細胞癌の際にも出現し高値を呈することから、肝臓癌の腫瘍マーカーとして利用されており、本件ガイドラインでも、肝細胞癌の補助診断に有用な腫瘍マーカーの一つとして推奨されている(強い推奨度)。
カットオフ値(陽性基準値)を40mAU/mLとした場合、特異度(その検査が陽性なら実際にその疾患である確率)が約95%であると報告されており、肝硬変等の良性疾患ではほとんど陽性を呈さない。ただし、ビタミンK製剤投与中は、肝細胞癌患者においても多くの症例でPIVKA-‹2›は正常化するため、腫瘍マーカーとしての利用はできないとされている。
3 経過
前提:患者は、他の病院にて、8年ほど、2型糖尿病の治療を受けていたが、腹部CTで肝硬変を指摘されたことから、同病院の紹介で被告病院を受診。
H26
8.9 患者、被告病院にて慢性肝炎及び肝硬変症と診断。
血液検査におけるPIVKA-‹2›は24mAU/mL。医師は肝機能につきChild-Pugh分類Bと評価。
12.29 患者、前日からろれつがまわらなくなり、自分が何をしているかわからないとの主訴で、 被告病院の救急外来を受診。血液検査の結果(アンモニア151μg/dL等)と、頭部CT検査では出血性病変等の異常所見は認められなかったことから、肝性脳症と診断。肝性脳症及び高アンモニア血症に対する治療としてカナマイシンの投与開始。
H27
3.28 肝性脳症及び高アンモニア血症に対する治療としてアミノレバンの投与開始。
8.1 PIVKA-‹2›は22mAU/mL。
H28
1.9 PIVKA-‹2›は53mAU/mL。
3.8 患者、慢性肝疾患の肝細胞癌探索のため被告病院にて腹部超音波検査実施。
肝臓右葉のS6/7に7×6mm大の高エコー領域が認められるも、経過観察。
4.9 患者、被告病院にて内分泌腫瘍検査実施。PIVKA-‹2›値が92mAU/mL。
6.11 患者、被告病院にて内分泌腫瘍検査実施。PIVKA-‹2›値が174mAU/mL。
8.12 患者、被告病院にて腹部CT検査実施。CT画像において肝臓に低吸収域が複数認められ、左 葉内側にも低吸収減が認められたが肝内に腫瘍は指摘できず肝細胞癌を思わせる異常はないと診断。
H29
1.20 患者、意識障害に陥り、被告病院へ救急搬送。搬送時に羽ばたき振戦が見られ、ややろれつが回っていない。血液検査の結果として血中アンモニア261μg/dLと高値であったこと、頭部CT検査で出血性病変や占拠性病変等が認められなかったことから、慢性脳症と診断。
4.8 患者、被告病院を受診。食欲低下と下肢のむくみの所見あり。
5.6 患者、被告病院を受診。浮腫の増強あり。
5.22 患者、被告病院に下腿浮腫に対するサムスカ(水利尿薬)投与の目的で入院。
5.24 患者、被告病院にて胸腹部CT検査実施。
肝臓左葉内側に長径82mm大の腫瘍が出現し、その中心部分は壊死を疑う造形不良域を形 成。肝細胞癌と診断。
5.27 腹部MRI検査実施。MRI画像から肝臓左葉内側に長径68mmの腫瘤があり、辺縁はダイナミック造影で早期濃染はなく漸増性の造影効果を示し、中心部には造影効果がなく壊死と思われ悪性腫瘍の所見と診断。
5.30 医師より患者とP1に対し患者の状態と治療方針に関する説明をしたところ、患者とP1はカテーテルから抗がん剤を注入する治療である肝動注化学療法(TAI)を受けることを希望。
6.3 患者、退院。
6.17 患者、被告病院に再度入院。
6.19 肝動注化学療法実施。
6.30 患者、被告病院を退院。
7.10 患者、家族の希望から被告病院に再度入院。
7.18 腹部造形CT検査実施。5月24日実施の画像と比較し、肝臓癌は増大傾向。
医師より家族に対し、今後動注療法による肝細胞がん治療はリスクの方が高いと説明。
7.24 患者、転院のため被告病院を退院。
7.25 患者、他院に入院後、冠動脈内カテーテル挿入、ポート埋め込み等の手術実施。
8.17 患者、死亡。死因は肝硬変症に起因する肝細胞癌。
4 争点
- 平成28年3月8日に造影CT、造影MRI検査をしなかった過失の有無
- 平成28年4月9日までに造影CT、造影MRI検査をしなかった過失の有無
- 平成28年8月12日に肝細胞癌を見落とした過失の有無
- 因果関係
- 損害の発生及びその額
5 裁判所の判断
1 争点1について
(原告の主張)
高エコー領域は肝細胞癌の所見として典型的ではないものの、慢性肝炎や肝硬変の患者では、血管腫様高エコー結節(高エコー領域)が肝細胞癌である場合もあるところ、患者には肝硬変の既往があったことも考えると、肝細胞癌が疑われる状態であった。 そのため、超音波検査で高エコー領域が認められた平成28年3月8日時点において、被告病院の医師は、患者に対し、肝細胞癌の鑑別のため、少なくとも造影CT、造影MRIの追加の画像診断を行うべき義務を負っていた。
(被告の主張)
超音波検査で認められた高エコー領域は、約7mmと小さく、やや高輝度の辺縁があまり明瞭ではない地図状の形態で、肝細胞癌のエコー像としては典型的でない。同部分は、肝硬変に伴う高度の線維化や再生結節の影響で描出された所見と考えられ、積極的に肝細胞癌を疑わせるものではない。後方視的にも、肝細胞癌ではなかったことが明らかとなっている。したがって、上記超音波検査の結果は、鑑別診断の対象とすべき「結節性病変が新たに指摘された場合」に該当しないから、被告病院の医師は、平成28年3月8日時点で、造影CT、造影MRIの検査を実施する義務を負わない。
(裁判所の判断)
原告らの主張によっても高エコー領域は肝細胞癌の所見として典型的ではないし、平成29年5月24日の胸腹部CT検査により発見された肝細胞癌等と異なる部位にあるから、後方視的にも肝細胞癌の所見ではなかったものと認められる。
そうすると、肝硬変に伴う高度の繊維化や再生結節の影響で描出された所見であると考え、経過観察の方針としたことに誤りがあるとはいえず、平成28年3月8日の時点で造影CT、造影MRI検査を行わなかったことが過失とはいえない。
2 争点2について
(原告の主張)
患者のPIVKA-‹2›は、平成27年8月1日は22mAU/mL、平成28年1月9日は53mAU/mLと半年以上にわたって単調に増加し、同年4月9日には92mAU/mLと、カットオフ値(40mAU/mL)を超える異常な高値となっていた。患者には肝硬変の既往があり、肝癌の発生リスクが高かったことからすれば、PIVKA-‹2›値の増加の原因としては、肝細胞癌が疑われた。したがって、遅くとも同日時点で、患者に対し、肝細胞癌の鑑別のため、造影CT、造影MRIの画像診断を実施すべき義務を負っていたが、被告病院の医師は実施しなかった。
(被告の主張)
患者の非代償性肝硬変によりビタミンK欠乏症が生じ、PIVKA-‹2›値が生じた可能性がある。また、当時、カナマイシン(主要な副反応の1つにビタミンK欠乏症がある。)の継続的服用により、PIVKA-‹2›値が上がった可能性がある。さらに、患者のPIVKA-‹2›値は平成28年11月12日の463mAU/mLをピークに低下しており、後方視的にもPIVKA-‹2›値の一時的上昇が腫瘍マーカーとしての上昇であったとは考えにくい。したがって、平成28年4月9日時点におけるPIVKA-‹2›値の上昇は、肝細胞癌を疑うべき所見とはいえないから、被告病院の医師には、同日時点で画像診断を実施する義務はない。
(裁判所の判断)
被告の主張を根拠に、平成28年4月9日までに造影CT、造影MRI検査を行わなかったことにつき、過失があるとはいえない。
3 争点3について
(原告の主張)
平成28年8月12日に実施されたCT検査のCT画像上、肝臓左葉に24mm大の占拠性病変が認められ、明らかな肝細胞癌の像で、これは典型的な肝細胞癌の造影パターンであった。患者が慢性肝炎及び肝硬変であり、肝細胞癌を発症しやすかったこと、患者のPIVKA-‹2›値が同年6月11日には174mAU/mLもの高値となっていたことも考慮するなら、被告病院の医師は、肝細胞癌を念頭に置き、CT画像上の所見に基づき、肝細胞癌と診断すべき義務を負っていた。それにもかかわらず、医師はCT画像の肝細胞癌所見を見落とし、肝細胞癌と診断しなかった。
(被告の主張)
CT画像上、低吸収域自体は確認できるが、それが直ちに腫瘍を示すものではない。患者は高度の肝硬変であり、肝臓には再生結節や肝嚢胞と考えられる多くの低吸収減が認められる。また、同CT画像は典型的パターンとは異なる。患者が慢性肝炎・肝硬変であることを考慮しても、CTからの診断が困難を伴うことに変わりはない。PIVKA-‹2›値の上昇は肝細胞癌を疑わせる事情にはならない。したがって、平成28年8月12日時点において、直ちに肝細胞癌と判断すべき所見があったとはいえない。
(裁判所の判断)
CT画像上の低吸収域は、高度の肝硬変によって生じた再生結節や肝嚢胞、アーチファクトでも認められるとされるところ、患者は、CT検査が行われた平成28年8月12日当時、Child-Pugh分類Cの肝硬変患者であったから、上記画像上の低吸収域は、CT検査当時の前方視的所見としては、肝硬変によって生じた再生結節や肝嚢胞の可能性もあったというべきである。また、本件ガイドラインによれば典型的な肝細胞癌の造影パターンではないところ、担当医師は典型的な肝細胞癌の造影パターンではなかったと陳述及び供述していること、CT画像の読影医も肝細胞癌を思わせる異常はないと診断していること、被告病院の消化器・肝臓内科のカンファレンスにおいても肝細胞癌の所見であるとの意見はなかったことも併せると、CT画像の所見から肝細胞癌と診断することは困難であったと認められる。したがって、被告病院の医師がCT画像の所見を肝細胞癌と診断しなかったことについて、過失があるとまではいえない。
4 争点4について
Child-Pughスコアは、平成28年3月12日に合計9点(分類Bに相当)となった以外は、10点ないし11点であり、患者の肝予備能は、同年3月8日、4月9日又は8月12日の各時点においてChild-Pugh分類Cであったものと認められる。そして、本件治療アルゴリズムによれば、肝予備能がChild-Pugh分類Cで、患者年齢が65歳を超える場合は、緩和ケアのみが推奨され、本件ガイドラインでも、Child-Pugh分類Cの肝細胞癌の場合に移植以外に推奨される治療はないとされているところ、患者は、平成28年当時、Child-Pugh分類Cで、年齢67歳(平成28年7月19日以降は68歳)であるから、同年3月8日、4月9日、8月12日のいずれの時点で肝細胞癌の治療を開始したとしても、緩和ケアのみが推奨されることになる。
以上によれば、被告病院の医師が、平成28年3月8日又は同年4月9日に造影CT、造影MRI検査を行い、若しくは同年8月12日にCT画像から肝細胞癌と診断していたとしても、患者について、肝切除術、ラジオ波焼灼療法(RFA)、肝動脈塞栓療法(TAE)、肝動注化学療法(TAI)等の積極的治療を行い、これが奏功して、平成29年8月17日よりも生存期間を延長することができた高度の蓋然性があるとは認められないというべきである。
争点5 判断なし